|
updated
|
|||
|
||||||||||||||
|
続き袖を考える 10
|
|||||
| 010 | |||||
| 【 袖の筒の作成 】 袖の目が完成しましたら合印を入れます。前後のカナメ位置を起点として袖山側、袖底側のイセ量を確認し、SPを設定し直します。それから袖の筒を作成します。 袖枠の前端線を直下させ、袖丈をとります。肘線はAe点から袖丈の1/2+1.0を袖口側からとります。肘線はウエストラインとほぼ同じバランスにありますからウエストラインから肘線を求めてもよいでしょう。 次に袖口で1cm前側に振りをつけます。これがこの袖の振りの基準となります。左図パターン参照 振りを設定した線で袖巾と袖口巾を同寸にした袖をつくると下のようなパターンになります。 |
||||||||||||
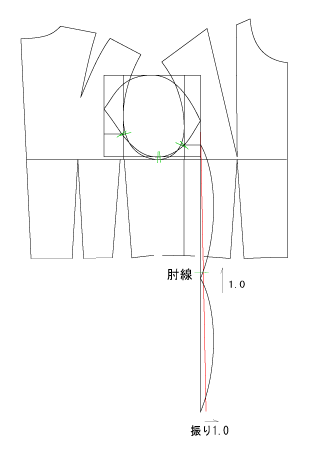 |
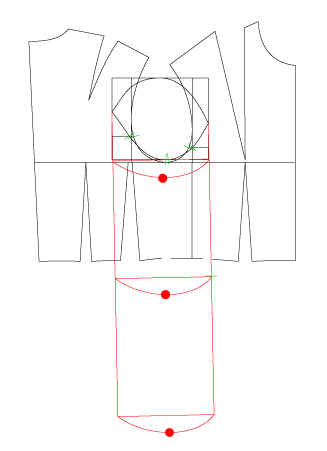 |
|||||||||||
| 次に袖口寸法を決め、ストレート袖から前後のカット量を決めます。
袖口の傾斜はブラウスでしたら、1cm、ジャケットでしたら1.5cmくらいをとり、袖口線を描きます。 袖下線は袖底点と袖巾1/2を通る位置に設定します。袖底を上げたことによって前後袖下線が重なっていますが、そのまま前後折り山線を軸に反転させます。下右図参照 地の目は肘線で1cm前振りにした傾斜で入れます。このように袖の振り線、袖下線、地の目線の3本の線の情報をパターンに入れておくことでその後の操作がスムーズになります。 |
||||||||||||
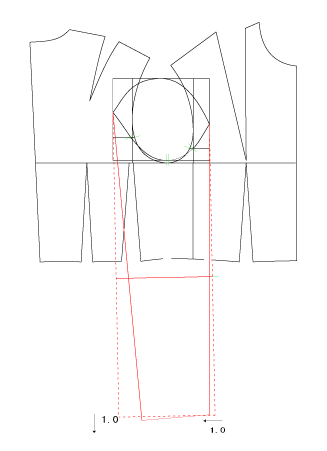 |
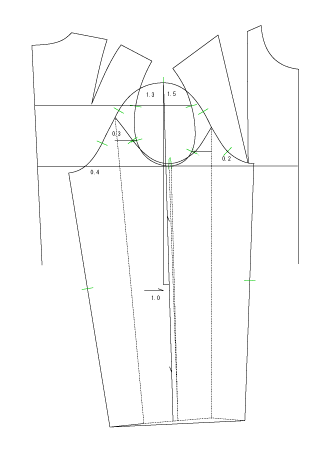 |
|||||||||||
 |
 |
 |
||||||||||
| back page | |||||||
| next page | |||||||
|
|
||
|
All right reseved Copyright(C)2003. iwaps.com |
||