|
updated
|
|||
|
|||||||||||||
|
続き袖を考える 31
|
||||
| 031 | ||||
| マチの構成 ここでマチの構造を再度確認してみましょう。 脇線と袖下線の交点bとマチ止りdを結んだ線を一辺とする同じ直角三角形が身頃側と袖側につくられています。 「b−d−a」「b−d−c」 袖下線と脇線のマチ止りの位置が変わっても、この三角形の構造は変わりません。 袖と身頃に同じ直角三角形ができることでマチの構成ができるわけです。
|
||||||||
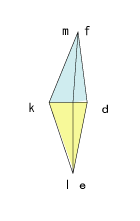 |
||||||||
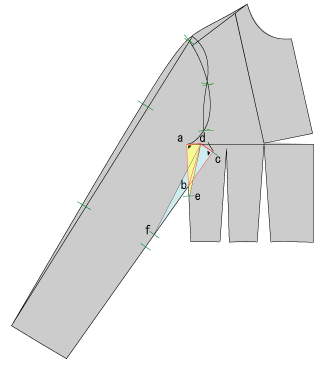 |
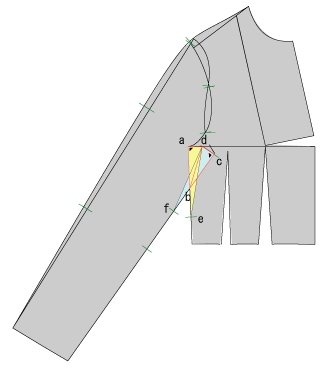 |
|||||||
| 同じ三角形ができるマチ製図方法をなぜ後ろ身頃ではわざわざ変える必要性があるのでしょうか。 では前身頃と同じ法で後身頃を作成するとどのような不具合が起きるかを確認してみましょう。 袖下線hから直角線を描き、aからの直角線と交わる点を求めます→k 求めたマチ止りk−aと、k−hの寸法を測ると同じではありません。 この状態ではマチ作成の条件となる同じ直角三角形が作れません。 前後袖の傾斜が違うため、後ろ身頃はaとhの直角線を交差した点kが等分となる点にはならないのです。 ここを等分にするために、一旦hとaを結んで二等分直角線をとります。 その交点をkとすると前身頃のように同じ三角形が後身頃と後袖にできます。 |
||||||||
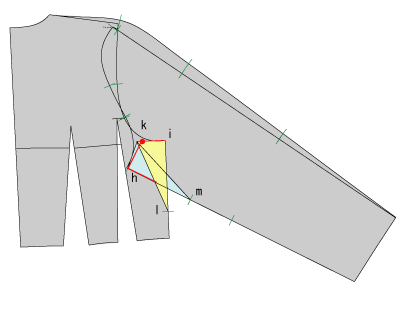 |
||||||||
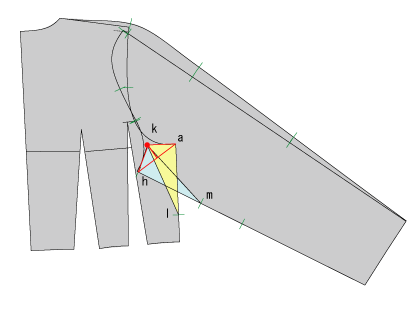 |
||||||||
| back page | next page | ||||||
|
|
||
|
All right reseved Copyright(C)2003. iwaps.com |
||